【犬の食糞】と腸内環境の関係は切り離せない!

しっかりとした良い便をしているにも関わらず、食糞をしてしまうのは、腸内で栄養がしっかり吸収されていないのかもしれません。食糞は、腸内環境と大きく関係しているのです。
便の状態を観察する日課は、正に、予防にあたります。しかし、私達は、目で見える事でなければなかなか納得できない動物でもあります。ところが、目で見える範囲は、氷山の一角であり、目に見えない事の方がとても大切になってきます。
目次
消化不良による食糞
未消化による食糞が考えられます。便は、腸内で栄養が吸収され、その余り物だと考えますが、この便の中に、本来、吸収されるはずの栄養が残っていれば、もちろん臭いを嗅ぎ付けエサと間違い食糞することが考えられます。
つまり、腸内で十分な栄養の吸収ができなければ、排便された便には、タンパクや脂肪が残ってしまいます。この様な、消化不良の便は、食糞の原因になってしまいます。
良い便だからといって、栄養を吸収しているとは限らない
ある程度硬くてしっかりとした便だから消化不良ではないように思われがちですが、そもそも便の形に大きく関わるのは、大腸での水分の吸収であり、水分の吸収がしっかり行われていれば、便はある程度硬い便になります。
しかし、この様な良い便であっても、小腸からうまく栄養が吸収されていない場合があるのです。なので、良い便だからといって、消化不良の便では無いとは限らないのです。
腸内環境を整え続ける意味
しっかりとした便の排泄、栄養を吸収し、水分を吸収すること、これは、腸内の良い菌(乳酸菌やビフィズス菌)などの善玉菌の力無しでは、順調に消化吸収を行う事ができません。
したがって便の状態が悪い(悪臭がする、軟便である、粘液便である、よく血液が付着する)ということは、腸内に異常が発生していることを意味し、善玉菌が減少している可能性が高いのです。
善玉菌の減少と共に悪玉菌が増殖すると、悪玉菌が産生する毒素により、腸粘膜は傷つき、タール便や血便になり、更に悪臭の便となり、内臓への負担も増加し、免疫力も低下してしまいます。
食糞や下痢軟便などの症状は、このように、後々、臓器にも負担を与えてしまいます。もちろん病気へとつながっていきます。食糞や下痢など、軽く思われがちな症状が、実は、体内で、目に見えない所で悪影響を与えている事をしっかりとイメージすることが、食糞や下痢等の早期改善に繋がり、病気の早期改善にもなるのです。
まずは、毎日の便をチェックし、腸内環境を整え続けることが愛犬を元気で長生きさせる第一歩になるのです。
今後の愛犬の健康にお役に立てれば幸いです。
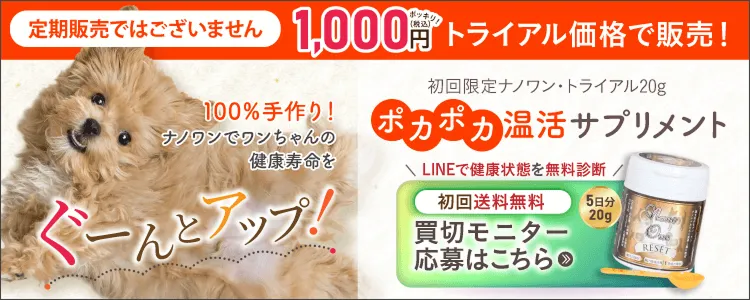
【 個別無料電話相談 】

■同じ下痢であっても、同じアルブミン低下であってもその子のこれまでの生活環境、食事、薬の経歴によって全くアドバイスが変わってきます。この子に合わせた個別アドバイスを受けられてはいかがでしょうか?
※無料相談では商品の購入は受け付けておりません。アドバイスのみとなります。また、お名前をお聞きすることもありません。安心してご相談ください。
※【 個別無料電話相談もございますが、お急ぎの方は直接ご連絡ください。】
※【 お問合せメールでのアドバイスは行なっておりません。お電話又はLINE電話のみの対応となります。ご了承ください。】
※ お急ぎの方は今すぐお電話ください。直ぐにコチラからかけ直します。
【電話受付時間】10:00〜16:00
【定休日】土日祝日(臨時休業あり)
年末年始、GW、夏季休暇
前の記事へ
次の記事へ




