犬も秋の花粉症には注意が必要!ただし人間とは少し症状が異なります

「やっと涼しくなったと思ったら目がかゆい!これはブタクサのせいに違いない!」とお怒りの飼い主さん。もしも愛犬がやたらと体を掻いたりフケが出ていたら、飼い主さんだけではなく、ワンちゃんも秋の花粉症の可能性があります。
人間の花粉症と犬の花粉症は、症状に大きな差はありません。しかし、人間の場合は目や鼻に症状が出やすいのに対し、犬の花粉症は皮膚に症状が出ることが多いのです。
目や鼻に症状が出ていないので「ちょっと体が痒いのかな?」程度で済ませてしまうと、いつの間にか皮膚症状が悪化して、さらなる皮膚病を呼び込んでしまうことも…。
目次
犬が花粉症になりやすい秋の植物は身近にたくさんある!
花粉症といえば「春」のイメージが強いですが、「秋」にもアレルゲンとなる植物はたくさんあります。たとえば…
- ブタクサ(キク科)
- アキノキリンソウ(キク科)
- ヨモギ(キク科)
- カナムグラ(アサ科)
- ギョウギシバ(イネ科)
- ホソムギ(イネ科)
- ススキ(イネ科)
- キンモクセイ(モクセイ科)
夏から秋にかけての花粉症といえば、真っ先にブタクサが思い浮かびますよね。しかし実際には、アレルゲンとなる花粉症をまき散らす植物は、いたるところに生えているのです。
街路樹のキンモクセイがオレンジの花を咲かせているので「きれいだなぁ、良い香りだなぁ」と通るたびに愛でていたら、実は飼い主さんや愛犬の花粉症の原因の可能性もあるわけですね。
まぁ、満開のキンモクセイは別にして、秋の花粉症の原因となる植物の多くは、なんというかどれも見た目が地味。いわゆる雑草と呼ばれるものばかりです。そのため、いつもの散歩コースにたくさん生えていたとしても、あまり気にすることがありません。
花粉症といえばスギがかなりの悪者にされていますが、実はアレルゲンは世の中のあちらこちらに生えています。そして、春から初冬までかわるがわるやってくるのです。

犬が秋の花粉症になったときの症状
花粉症といえば、目の痒みや大量の鼻水、クシャミ連発などのイメージがありますね。犬の花粉症も基本的に、人間の花粉症と大差はありません。
ただし、目や鼻より皮膚に症状が出やすい傾向にあります。もしも次のような症状が愛犬にみられたら、秋の花粉症の可能性を考えたほうがよさそうです。
犬の花粉症:皮膚の症状
犬の花粉症は皮膚に症状が出やすいので、次のような行動がみられたら、掻いたりなめたりしている部分をしっかり観察してください。
- 体をやけに掻いている
- 体の一部分をしつこくなめている
- 皮膚が赤くなっている
- 皮膚に発疹ができている
- 被毛や皮膚が妙にべたついている
- 耳の中をやたらと掻く
- 耳の中が赤くなっている
こうした症状を放置していると、秋の花粉症が引き金となって膿皮症・マラセチア皮膚炎・アトピー性皮膚炎など、さらなる皮膚病を引き起こす可能性があります。
犬の花粉症:目の症状
人間の花粉症では目の充血や結膜の炎症などがみられますよね。しかし犬の花粉症においては、結膜の炎症などはかなりの少数派です。
犬の花粉症の場合は、目そのものの症状ではなく、目の周囲の皮膚に症状が出ることがほとんどと言えるでしょう。つまり、目を掻いているように見えても、実は目の周囲の皮膚を掻いているわけですね。
そのため、もしも目やにが多く出ていたり涙の量が増えているとしたら、その原因は秋の花粉症ではないのかもしれません。このあたりの判断は、かかりつけの獣医師に任せるのが一番です。
犬の花粉症:鼻の症状
人間の花粉症ではクシャミと鼻水が鉄板ですよね。しかし犬の花粉症では、クシャミと鼻水が酷くなることは滅多にありません。
ただし、大量の花粉を吸い込んでしまった直後に、クシャミを連発したり鼻水が出ることはあります。この場合は鼻の中に異物が残ってしまったことで、炎症を起こす可能性が危惧されます。
いずれにしろ、クシャミを連発して鼻水が大量に出ている時は、かかりつけの動物病院へ直行しましょう。鼻腔の奥に種が突き刺さってしまい、それが原因で細菌感染した場合、最悪は命をおびやかすこともあるのです。
>『犬のフィラリア予防薬とノミ・マダニ駆虫薬|必要性とデメリット』

愛犬の秋の花粉症を防ぐために飼い主としてできること
これをすれば犬の花粉症を100%防げる!…という方法はありません。その方法があれば、人間がこれほどまでに花粉症で苦労しませんよね。
とはいえ、できるだけ花粉症にかかるリスクを軽減してあげることはできるはずです。
花粉が飛散しやすい日や時間帯をできるだけ避ける
愛犬の花粉症を避けるには、花粉と接触させないのが一番です。とはいえ、花粉が怖いからと散歩に行かないのは本末転倒ですよね。となると、一番の対策方法は花粉の飛散量が多くなるタイミングを避けることです。
- 気温が高い日……花粉が付いた雄花が開きやすい
- 湿度が低い日……花粉が空気中を漂いやすい
- 風が強い日……花粉が広範囲に拡散しやすい
- 雨の翌日に晴れた日……一度地面に落ちた花粉が舞いやすい
- 日中の気温が高い日が続く時……花粉の飛散量が増加しやすい
- 日没の前後……上空に舞い上がった花粉が気温の低下で落下しやすい
上記のすべてを避けることは、なかなかに困難でしょう。しかし、こういうタイミングは花粉の量が多くなると知っているだけで、最悪の時間帯は避けることができそうです。
散歩のルートを変更して、できるだけ草の多い場所を避ける
いつも草むらの多い道をお散歩のルートにしているなら、花粉の多い時期や時間帯は、草むらの少ない道にルートを変更するのも良い方法です。
特に土手には花粉症の原因となりやすいイネ科やキク科の植物が自生しているので、ブタクサ全盛期などは避けた方が無難。河川敷や空き地なども同様です。
洋服を着せて愛犬の体に付着する花粉をブロックする
洋服を着せることで、愛犬の体に直接花粉が付着するのを防止するのも良い方法といえるでしょう。できれば静電気防止加工がされている洋服を選ぶと、より花粉の付着を防ぐことができます。
ただし、洋服を着せっぱなしにしたのでは意味がありません。
散歩に行く前に洋服を着せ、散歩から帰ってきたら洋服を脱がせることが重要です。ここを怠ると、洋服に付着した花粉を家の中に持ち込むことになるので、意味はないどころか逆効果になりますよ!
散歩から帰ったら愛犬の体に付着した花粉を落とす
散歩から帰ってきたら、ブラッシングや濡れタオルで拭くなどして、愛犬の体に付着した花粉を取り除いてあげましょう。
その際には、体だけではなく顔面もしっかり拭き上げることが大切。というのも、犬の花粉症は目や耳などに症状が出ることが多いからです。
また、ブラッシングをするときは静電気防止効果のあるグルーミングスプレーを使うと、より花粉の付着を防止することができます。

腸内環境を整えることが愛犬の花粉症を軽減させる
愛犬の腸内環境がよくないと、花粉症にかかりやすくなります。なぜなら、腸内環境が悪玉菌優勢の悪い状態だと免疫システムが過剰に反応してしまい、その結果として花粉症を悪化させてしまうからです。
花粉は、本来であれば犬の体にとっては無害なもの。ところが腸内環境の乱れによって免疫システムに狂いが生じてしまうと、体は無害なはずの花粉を異物とみなして過剰な攻撃をしてしまうのです。
だからこそ、免疫システムを正常に戻すためには、腸内環境の改善が必要なんですよね。つくづく、腸内環境は犬の健康を左右しています。
>『【現代の犬の健康】は、腸を温める食事の継続が必須条件となる』
今後の愛犬の健康にお役立て頂ければ幸いです。
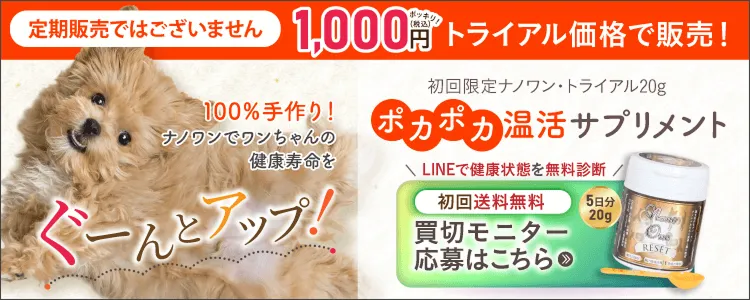
【 個別無料電話相談 】

■同じ下痢であっても、同じアルブミン低下であってもその子のこれまでの生活環境、食事、薬の経歴によって全くアドバイスが変わってきます。この子に合わせた個別アドバイスを受けられてはいかがでしょうか?
※無料相談では商品の購入は受け付けておりません。アドバイスのみとなります。また、お名前をお聞きすることもありません。安心してご相談ください。
※【 個別無料電話相談もございますが、お急ぎの方は直接ご連絡ください。】
※【 お問合せメールでのアドバイスは行なっておりません。お電話又はLINE電話のみの対応となります。ご了承ください。】
※ お急ぎの方は今すぐお電話ください。直ぐにコチラからかけ直します。
【電話受付時間】10:00〜16:00
【定休日】土日祝日(臨時休業あり)
年末年始、GW、夏季休暇
前の記事へ




