愛犬の体にマダニを発見!むしり取るのは絶対にダメ!

犬がマダニに寄生されると危険――。と、頭ではわかっているつもりでも、その実ピンときていない飼い主さんも多いのではないでしょうか。
ノミと同じような吸血性の昆虫と思われがちですが、マダニは昆虫ではありません。8本足のマダニは節足動物門に分類される、クモやサソリの仲間です。
マダニに寄生されると最悪命を落とすこともありえるため、寄生されないように手を尽くすべきですが、どうも日本では危機感に乏しいような…。
というわけで、今回はマダニの怖さについてしっかり見ていきましょう。
目次
犬の健康を脅かすマダニは日本全国どこにでも生息している!
マダニは世界中に生息しています。つまり、マダニの被害はある意味世界規模なわけですが、日本に比べてアメリカやオーストラリアのほうが危機感が強いのは間違いありません。
それもそのはず。アメリカやオーストラリアに生息しているマダニの中には、唾液腺から強烈な神経毒を出すタイプがいるからです。この種のマダニに犬が咬まれると体の麻痺や呼吸麻痺などが引き起こされ、最悪は死に至ることも。
今のところ、神経毒によって運動麻痺や呼吸麻痺を引き起こすタイプのマダニは、アメリカとオーストラリアに集中しています。しかし、だからといって日本のマダニを軽く考えてよいわけではありません。
日本にも10種類以上のマダニが生息していますが、その分布は北海道から沖縄まで全国津々浦々。北から南まで見事に網羅されています。
もしかしたら、近い将来麻痺性の毒を持ったマダニが日本で発見されるかもしれません。外国の話だとのんびり構えているわけにはいかないのです。

マダニの真の怖さは人獣共通感染症を媒介すること
マダニは幼虫・若虫・成虫のいずれにおいても吸血をおこなう外部寄生虫です。そのため、体の小さな小型犬が大量のマダニに寄生されてしまうと、貧血によってかなりの体調不良に陥ることは珍しくありません。
また、マダニの出す唾液がアレルゲンとなり、強烈な痒みを伴う厄介な皮膚炎を引き起こすことは、わりとよく知られているのではないでしょうか。
しかし、マダニの寄生によって引き起こされる病気はそれだけではありません。
なにより厄介なのは、人獣共通感染症の病原体を媒介する可能性があることです。しかも媒介する感染症は一つではなく、人間が感染すると致死率が高いものまであります。
マダニが媒介する病気:犬バベシア症
マダニの体内に潜んでいるバベシア原虫が、犬の赤血球に寄生することで発症する感染症です。赤血球が破壊されてしまうため、貧血・発熱・食欲不振などを引き起こし、急激に症状が進んでしまうと黄疸・衰弱によって命を落とすことも。
いまのところ、日本国内では比較的病原性弱めのバベシア症が多く報告されています。しかし、いつなんどき病原性の強いバベシア症が流行するとも限りません。
マダニが媒介する病気:ライム病
マダニが保有しているボレリア菌によって発症します。犬が感染した場合は比較的軽症で済むことも多いですが、厄介なのは人間に感染した場合です。
最も多くみられるのは遊走性紅斑と呼ばれる症状で、刺された部分の赤い斑点がどんどん広範囲に広がっていきます。しかし、この症状は単なる始まりの合図でしかありません。
発熱・悪寒・頭痛・筋肉痛・関節の腫れと痛み・リンパ節の腫れ・背中の痛み・嘔吐・顔面麻痺などなど、とにかく具合の悪い状態が数週間程度続くため、完治までにかなりの時間を要する感染症です。
マダニが媒介する病気:Q熱
リケッチアの一種であるコクシエラ菌に感染することで発症します。(※リケッチア/ウイルスより大きく細菌より小さな微生物)
犬が感染してもあまり目立った症状は出ませんが、人間が感染してしまうとかなり厄介なことになります。
高熱・激しい頭痛・筋肉痛・強い倦怠感などにおそわれるため、インフルエンザと勘違いされることもありますが、適切な治療をしないと肺炎や肝炎などを引き起こすことも。
また、急性型Q熱を発症した人の1~2%は心内膜炎が慢性型に移行してしまい、それが慢性疲労症候群の原因になっているのではないかと指摘されています。
マダニが媒介する病気:重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
ブニヤウイルス科フレボウイルス属に分類される新しいウイルスをマダニが媒介することで引き起こされる感染症です。
日本でも2013年に死亡例が確認されており、人間に感染した場合の致死率は6.3%~30%と高い数値が報告されています。
主な症状としては発熱・食欲低下・嘔吐・下痢・腹痛などの消化器症状ですが、頭痛や筋肉痛などを伴うことが多いようです。
また、失語や意識障害などの神経症状だけではなく、リンパ節に血液成分が溜まって腫れあがる・皮下出血・下血といった出血症状がみられることも。
さらには白血球減少・血小板減少・AST/ALT/LDHの血清逸脱酵素上昇などなど、ここでは書ききれないほどの体調悪化に見舞われることになるでしょう。
しかも、感染経路はマダニによる媒介が多いものの、人から人への感染例も報告されており、いまのところ有効なワクチンや治療薬がないという恐ろしい状況です。

マダニが生息しているのは山奥だけではない!
「うちは犬を山や森には連れていかないから、マダニに寄生されることはない」――などと悠長にかまえていてはいけません!
マダニの生息地
・山・森・林
・河川敷
・公園の草むら
・道路の植栽や花壇
そうなんです。マダニは草むらさえあれば、どこにでも生息している可能性があるんですね。決して山奥だけに限ったことではありません。
愛犬を散歩させているいつもの公園、毎日通っている道沿いの花壇、もしかしたら自宅の庭にだってマダニは潜んでいるかもしれないのです。
室内飼育だからといって油断は禁物。昨日までは無事に過ごせていたとしても、今日マダニが大切な愛犬に寄生するかもしれません。
愛犬の体にマダニを見つけたら、絶対にむしり取ってはいけない!
吸血前のマダニは約3~8mm程度と小さいですが、たっぷり犬の血液を吸ったあとでは10倍もの大きさに膨らみます。
ブルーベリーのようなサイズになることから肉眼ではっきり見えてしまうため、見つけ次第むしり取りたくなるでしょう。しかし、絶対に焦ってはいけません。
なぜならマダニは吸血のために皮膚の奥深くまで口を突き刺し、さらには簡単には抜けないようにセメントのような成分を出して口を固定しているため、無理にむしり取ると高確率で頭部が皮下に残ってしまうからです。
すると皮下に残ったマダニの頭部が原因で化膿したり、最悪はウイルス感染を引き起こすことも。
また、寄生しているのがメスのマダニだった場合、お腹の中には数千個もの卵をかかえています。むしり取ったマダニを不用意に潰してしまうと、この卵が飛散することになるため注意しなければなりません。
というわけで、愛犬の体にマダニが食いついているのを見つけた時は、憎さのあまり無理矢理むしり取りたくなる気持ちをぐっと抑え、とりあえずかかりつけの動物病院に直行することをおすすめします。

マダニ予防薬の効果をあげるには腸の健康維持が欠かせない
厄介で恐ろしいマダニの寄生ですが、お薬で予防することは可能です。ただし、腸の状態がよくなければ、マダニの予防薬を服用したところで成分がしっかり体に吸収されません。
腸内環境を常に良い状態に保つことこそが、愛犬の体を守ることにつながります。
腸内環境の改善は3つのポイントについてはこちらの記事で詳しく説明しています。
今後の愛犬の健康にお役立て頂ければ幸いです。
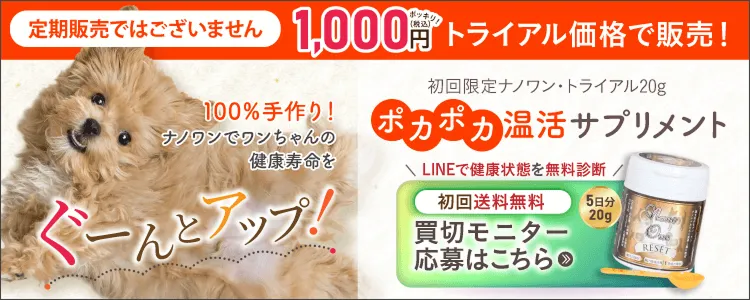
【 個別無料電話相談 】

■同じ下痢であっても、同じアルブミン低下であってもその子のこれまでの生活環境、食事、薬の経歴によって全くアドバイスが変わってきます。この子に合わせた個別アドバイスを受けられてはいかがでしょうか?
※無料相談では商品の購入は受け付けておりません。アドバイスのみとなります。また、お名前をお聞きすることもありません。安心してご相談ください。
※【 個別無料電話相談もございますが、お急ぎの方は直接ご連絡ください。】
※【 お問合せメールでのアドバイスは行なっておりません。お電話又はLINE電話のみの対応となります。ご了承ください。】
※ お急ぎの方は今すぐお電話ください。直ぐにコチラからかけ直します。
【電話受付時間】10:00〜16:00
【定休日】土日祝日(臨時休業あり)
年末年始、GW、夏季休暇
前の記事へ




